本書を読み進めるうちに「自伝的作品」という言葉が頭にちらつきます。
この物語は作者の半生を描いているのだろう・・・という意味ではなく、それが文章にせよ音楽にせよその他どのような手段にせよ表現に関わりたがる人間たちすべてに共有可能な、身に覚えのある痛みに充ちていると思ったからなのです。
あらすじと特徴
「まるで骨の中で暮らしているみたい」
ニュータウン計画に則って際限なく拡張して行くその街は、その新しさを印象付ける白色に統一されています。
物語はそんな「しろいろの街」に生きる主人公結佳の小学生から中学生に至るまで、つまり第二次性徴の芽生えとそれに伴って訪れる価値観の変遷を描いて行きます。
家庭や学校に大きな問題がないにもかかわらず、結佳は周囲に対する違和感を内に秘めつつ、息をひそめるようにして暮らしています。やがて同級生の男子生徒伊吹に対する恋愛感情を抱き始めた彼女は、そのいびつな想いを持て余し始めるのでした…。
『コンビニ人間』や『殺人出産』などで顕著にみられるように、村田沙耶香作品と言えば衝撃的かつ逆説的な世界観が設定された作品をイメージされるのではないでしょうか。その主人公たちも一見私たちとはかけ離れた人格や思考の持ち主であることも多く、それゆえに村田作品にとっつきにくさを覚える方も多いのではないでしょうか。
しかし本作の世界は紛れもなく私たちが生きる世界そのものであり、舞台となるのもどこにでもありそうな住宅街であり、主人公もどこにでもいそうな一人の平凡な少女にすぎません。その物語展開にも、はっきり言って私たちをあっと言わせる衝撃的な展開や結末があるとは言えません。
そういう意味では数ある村田沙耶香作品の中で、もっとも静かでノーマルな物語であると言えるでしょう。しかし同時に、もっとも激しくアブノーマルな物語とも言えるのです。
身に覚えのある痛みたち。そして言葉。
さて、多くの人々にとって馴染み深いであろう学生生活ですが、生来の人嫌いである私にとってはあまり馴染みがあるとは言い難いシチュエーションではあります。なので本作で展開する「学生生活」を核とする物語にどれほどのリアリティがあるのかわかりかねるところではありますが、それにしても主人公が味わう息苦しさ窮屈さがまるでかつて味わったものででもあるかのように迫ってくるのは、きっと主人公をはじめとする登場人物たちが狭い世界で自意識を肥大させ続ける私たち自身の戯画であるからなのでしょう。
私たちもまた白くて清潔な「牢獄」のなかで、誰に割り振られたわけでもないのにそれぞれの役割を演じ、誰に着せられたわけでもないのに囚人服のような正しい価値観をまとって他人を裁き自分をも裁きますが、どれほど無視に努めても自分自身の価値観や感情というものはいつかどこかで滲み出して行きます。
恋愛感情はこじらせすぎると嘔吐物になるのかもしれない。私は、ずっと、この感情を嘔吐したかったのかもしれない。
主人公結佳の歪な恋愛感情が核となって行く物語ですが、もちろん本作は「恋愛小説」で終わってしまう物語ではありません。愛も憎しみも殺意も慈愛も、すべての感情は恋愛感情と変わるところがないのですから。あらゆる感情は一度生まれたが最後、制御不能でどこまでもこころの奥底に食らい込み、私たちはいつでもどこでもそれを嘔吐する場所を探しているのではないでしょうか?
みんなが受容しているこの光景に、「不気味」という言葉を使ってもいいのだと、ぼんやり思っていた。
感情を嘔吐するということは、白くて清潔な価値観に汚物のシミをつけることでしょう。そのシミは悪臭を発する醜悪なものに他なりませんが、それを生み出した「身に余る切実」は何物にも代えがたい美しいものです。
白い世界は光の水でできていて、触ると波紋になって広がっていく、白い光の世界で、私は世界に少しずつ触れて、自分が作った水紋を見つめる作業に熱中しはじめていた。それが楽しいのは、今まで自分が一度もその水紋を見たことがないからかもしれなかった。
私は自分が傷つかない程度の波紋の中で、それにうっとりと見とれながら、光の世界で過ごし始めていた。
自ら言葉を選び取ることで新たな傷を負って行く結佳の姿はこの上なくすこやかで、のびやかで、美しくて、まぶしくて、うらやましい。自らを見つめ、自らの傷を見つめ、それらを言葉で描き出して行くことを選んだ結佳とともに、彼女の世界は再び動き始めて行くのです。
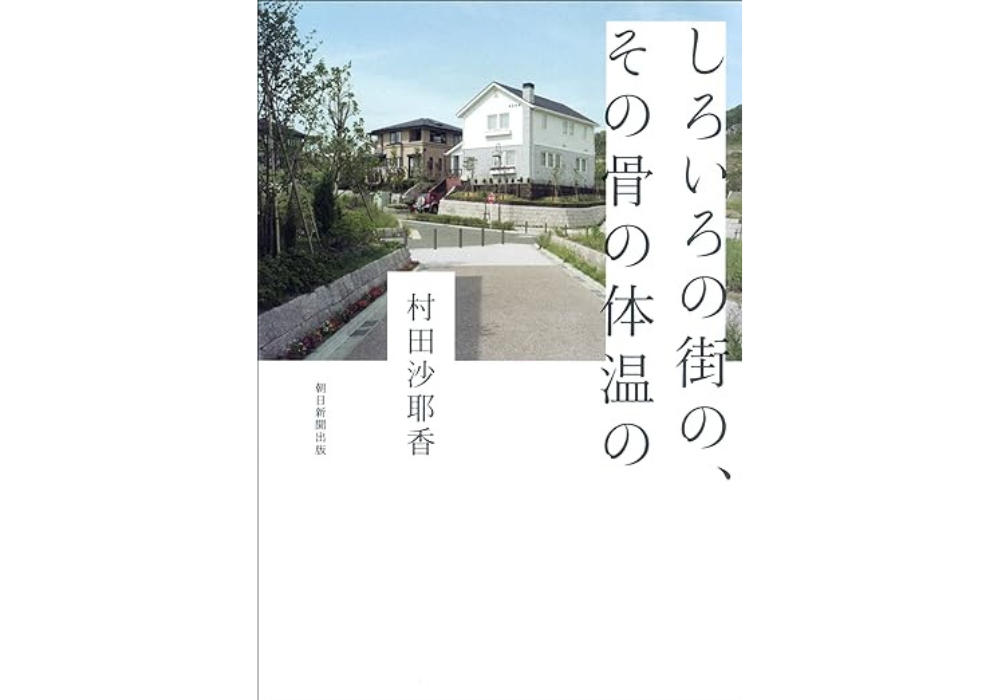

コメント